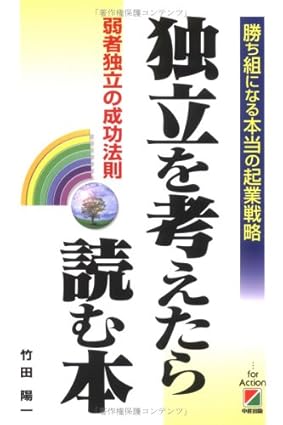社労士として開業したいけど、何をしたら良いかわからないし、上手くいくか不安。
開業に失敗する理由ですが、
「集客できないから」が、100%
です。
お客がいれば、経営は続けられます。
なので、
開業前の半年~1年
は、じっくり集客の準備をして下さい。
すでにお客さんがいる方は、
即・開業
で問題ありません。
失敗しないための「社労士の独立・開業のヒント」
開業を成功させるなら、何をどう検討しないといけないか?をお届けする無料メール講座です。
まずは、月商30万→50万→100万円と徐々に上を目指しましょう。
開業で失敗しないために必要なことが判ります。
開業前に知って欲しいこと
開業して売上が作れず、お金が無くなって
「こんなはずじゃなかった」
にならないために、事前に知って頂きたいことは、
- なんとかなるは、危険
- 開業前から、経営戦略の研究と集客準備が大事
- 集客できるなら、むしろ開業はおすすめ
です。
開業は、「なんとかなる」では危険な理由
経営を続けていくには、お客さんが必要です。
お客を獲得できないのに
「社労士の資格取って開業したら、なんとかなる」
は、あり得ないです。
社労士で新規客の開拓って、かなり大変です。
社労士の集客は、ハードル高めな理由
社労士の集客は大変です。
なぜなら、
対象のお客さんが少なく、新人社労士には乗り換えづらい仕事だから
です。
例えば、給与計算
例えば、給与計算だと、10人以上でないと外注しません。
また、100人規模になると経理が給与計算ソフトを使って自前でやってしまいます。
さらに新人社労士に、いきなり給与計算を依頼することもないです。
年々、ライバルが増える
お客が少ない市場に、
先輩はいるし、毎年、合格者が出るのが社労士
です。
競争が激しいです。
開業当初は、失注・失注の連続になります。
正直にいうと、
問合せすらない状態
が続きます。
これがキツいです。
独立・開業した社労士の先生にも、お聞きしましたが、
1年は、我慢
2年は、辛抱
3年で、モノにならなければ、借金だらけになる前に廃業したほうが良い
ということでした。
「なんとかなる」で開業すると・・・
「なんとかなる」で何も考えずに開業すると、
最初の1案件目の獲得
まで、
半年から、1年くらいの時間がかかる
と思います。
「廃業率」はアテになりません。
ちなみに、廃業率を気にする人もいます。
ですが、社労士登録だけして、他の仕事してる社労士さん大勢います。
なので「廃業率」はアテになりません。
あなたが続けられるかどうか?
が大事です。
タイムリミットは、半年くらい
今まで「経営」について全く考えたことが無い場合は、
半年~1年かけて研究
してみて下さい。
1年以上掛けると、
次の年の、社労士合格者
が出て、さらにライバルが増えます。
社労士試験の合格後、すぐに研究を始めて、
次の年の合格者がでる「10月」までに開業が理想
ですね。
おすすめの経営戦略の入門書
「開業するなら、経営戦略が必要そうだ・・・」
と感じたあなたに「おすすめの経営戦略の入門書」は、
竹田ランチェスター戦略
の
何を売るか・どう売るか。独立・起業の成功戦略CD(CD-ROM、テキスト、書籍付)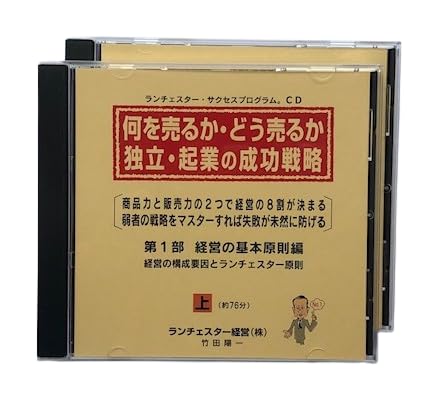
と
です。
後から、市場に参入しようとする側が、
どうやって先発者を追い抜かしていくか?
の方法が解説されています。
[ 今すぐ、【何を売るか・どう売るか。独立・起業の成功戦略CD】を購入したい方はこちら ]
(開業しなくても、買って損は無いです。)
開業後に「必要な資金」が見える
「何を売るか・どう売るか。独立・起業の成功戦略CD」の中では、
あなたが開業したら、何か月くらいで、軌道にのるか?の判定
が「自分で」できるようになっています。
半年で軌道に乗るなら、半年分の運転資金を用意できれば、開業できます。
2年かかるようなら、2年分の運転資金、生活費を用意しなければいけません。
成功しやすい開業の仕方が判る
また
「あなたが成功しやすい開業の仕方とは、どういうものか?」
の判定も出来ます。
1度確認してみてください。
[ 今すぐ、【何を売るか・どう売るか。独立・起業の成功戦略CD】を購入したい方はこちら ]
(開業するなら、買って損は無いです。)
開業は、集客ができれば、全く怖くない
開業で不安に感じるのは、お金のことだと思います。
ですが、お客がいれば、お金も途切れることはありません。
- 経営戦略をしっかり練り、
- 集客作業にじっくり取り組み、
- 顧問契約を積み上げる
ことができれば、
社労士は安定した経営が可能
です。
(「何を売るか?」によりますが、年商1,500万円の社労士事務所もあります。)
後悔しない開業準備をするための無料メール講座
「こんなはずじゃなかった・・・」にならないために開業前に準備することとは?
「なんとかなる」で開業して、失敗する人は沢山。
お金と人生を失う前に、必要な事前研究について無料で解説。
開業計画をしっかり立てて、3年の苦労をすっ飛ばす
1年、2年、3年と苦労はしたけど、
成功してる社労士さん
はおられます。
その
3年の苦労をすっ飛ばす
ことができるのが
経営戦略に基づいた独立・開業
です。
実務は、他の社労士さんに替わりにやってもらうなどで、なんとでもなります。
ですが、依頼主の獲得が大変なんです。
まずは、
集客できる社労士
に向かって、一歩を踏み出しましょう。
そうすれば、あなたも独立・開業が成功する社労士になれます。
何を売るか・どう売るか。独立・起業の成功戦略CD
(CD-ROM、テキスト、書籍付)
※アマゾンで販売中は書籍無し
を手に取ってみて下さい。
今、購入しなくても、開業後に苦労したら、思い出してください。
必要な方向けに開業準備サポート
- 何を売るか・どう売るか。独立・起業の成功戦略 CD2巻 テキスト付
をご購入されて、竹田ランチェスター戦略をベースに社労士として開業をご検討している方に、必要なら
- 集客できるホームページの制作(税込・6.6万円の1回払い、テンプレートを使って省エネ製作になります。)
- 竹田ランチェスター戦略を、ご自身の開業に具体的にどう活用するか?の「開業相談」
をさせて頂きます。
開業後の集客支援
また、開業後は、
- ホームページの運用・ネット集客代行
- 経営顧問契約を取るために、竹田ランチェスター戦略の理解を深める勉強会
(開業後に孤独になりがちな社労士さんの異業種交流会も兼ねてます。社長の気持ちが判るのでオススメです。)
で、安定した集客、事業運営をしつつ、
顧問契約を積み上げる
お手伝いをさせて頂きます。
ぜひ、一緒に月商50万・100万円を超える社労士になっていきましょう。
経営戦略の研究は、顧問契約を獲るためにも必要
顧問契約自体は、税理士さんが取ってしまいがちです。
それで、社労士は、税理士さんからの
おこぼれの単発仕事
が多くなるんですね。
これだと、経営がものすごく不安定です。
「それでもいい」ということなら税理士法人に勤めれば良い話です。
社労士として、独立開業する必要はありません。
経営の勉強は、自分のためでもありますが、
顧問契約を獲るためにも必要
ということを理解しておいてください。
「税理士さんの下請け」になるか、「経営の先生」になるかで単価も全然違います。
他の社労士さんと差別化を図る意味でも
経営戦略をマスターし、お客さんに経営指導
ができるよう今のうちに準備しておきましょう。
集客はネットがオススメ
社労士とは全然違う業種から開業する場合、人脈もコネもありません。
営業経験もないという場合は、ネットを活用するのがオススメです。
「ネットで集客なんてできるの?」
ですが、
今、あなたはネットで、このページを見ている
んですよね?
あなたの見込客も同じように、あなたのホームページやブログ、SNSを見るということです。
戦略に沿った集客術の活用は、
お客さんを自動で
連れて来てくれます。
あとは、経営戦略を研究して、自分なりの戦略を立てるだけです。
「ひよこ喰いビジネス」をする気はありません
開業する人を喰いものにする
「ひよこ喰いビジネス」
というのがあります。
社労士の開業塾や、開業予備校みたいなところには「開業させるのが目的」の商売をしているところもあります。
「開業させたら、あとは知らん」ですね。
そういうところは「実務」や「精神論(心構え)」が中心で、そこで開業した方は、集客できずに酷い目に逢ってます。
そうならないために、「開業後も役に立つ」情報発信をしています。
月商100万円を目指す社労士向けの無料のメール講座への登録はこちらから
竹田ランチェスター戦略をベースにした社労士さんの開業サポートをする理由
ネット集客実践クラブが、竹田ランチェスターをベースにした社労士さんの開業サポートをする理由は、
あなたの力で世の中の企業を、どんどんホワイト化してほしいから
です。
これができるのは人事・労務のプロ、社労士さんしかいません。
そして、ホワイト化するには、その企業自体が儲かる必要があります。
竹田ランチェスター戦略を学び、ご自身の顧問企業を儲けさせつつ
人事・労務面と、経営面でサポートする人材を増やしたい
というのが、我々の願いです。
社労士として開業するというあなたをサポートすることで、共に
ホワイトな会社を増やしていきたい
と願っております。
「何を売るか・どう売るか。独立・起業の成功戦略CD・独立起業セット」は1万円近くしますが、手に取って頂き、
ぜひ
経営支援もでき、尊敬される社会保険労務士
として開業して頂ければと思います。
月商100万円を目指す社労士向けの無料のメール講座への登録はこちらから
特定商取引法に基づく表記
- 販売業者
-
エフズ商店
(ランチェスター経営大阪・販売代理店) - 所在地
-
〒586-0001
大阪府河内長野市木戸1-37 - 商品代金以外の料金の説明
- 販売価格とは別に配送料、代引き手数料、振込手数料がかかる場合もございます。
- 不良品
-
情報データ、勉強会などは、商品の性質上、返金には応じかねますのでご了承ください。
ランチェスター経営商材に関しては、正品と交換させて頂きます。 - 販売数量
- 各商品ページにてご確認ください。
- お支払い方法
-
集客サービスについては、 銀行振込になります。
勉強会・セミナーに関しては、講座会場で直接「現金」にてお支払いください。
ランチェスター経営商材に関しては、「銀行振込」「代引きクレジット」が可能です。 - お支払い期限
- こちらの指定期日までにお支払いお願い致します。
- 返品期限
- 商品の性質上、返金・返品には応じかねますのでご了承ください。
※上記以外の事項に関しましては、お取引の際に請求があれば遅延なく提示いたします。